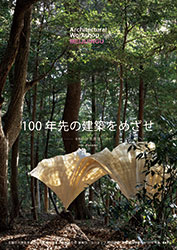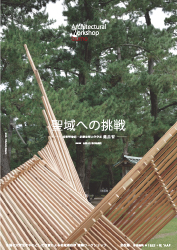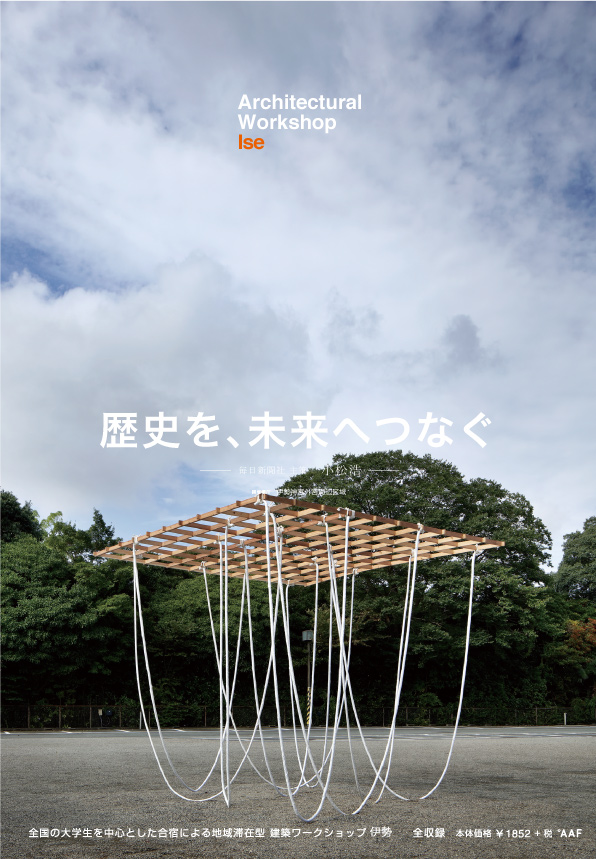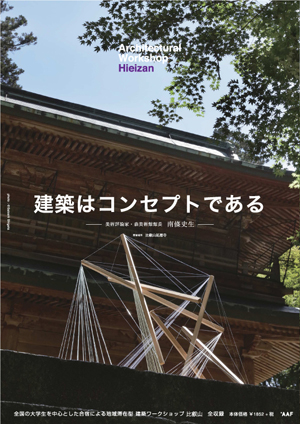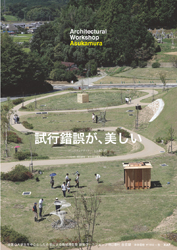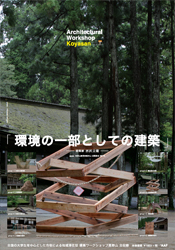|



|

6/28(土) 各班エスキース 東京会場(東京大学)&大阪会場(平沼孝啓建築研究所) |
|||||
各班の作品のクオリティを高める目的で始まった取り組みとして「各班エスキース」を開催させていただきました。東は東京大学・生産技術研究所にて、腰原先生、櫻井社長、長田先生、安原先生、佐藤先生、吉村先生がご参加くださり、西は平沼孝啓建築研究所にて、陶器先生、片岡先生、平沼先生がご参加くださいました。会場間をzoomで中継し、先生方より、提案作品への貴重なご指導を賜りました。 |
|||||
 |
 |
||||
| 東京会場の様子① |
大阪会場の様子① |
||||
 |
 |
||||
| 東京会場の様子② |
大阪会場の様子② |
||||
 |
 |
||||
| 東京会場の様子③ |
大阪会場の様子③ |
||||
 |
 |
||||
| 東京会場の様子④ |
大阪会場の様子④ |
||||

6/7(土) 現地説明会・調査 |
||
現地にて、各計画候補地の視察と調査を行い、課題テーマに対するコンセプトを発表しました。 |
||
 |
||
| 集合写真
|
||
 |
 |
|
| 2025日本国際博覧会協会副事務総長・田中様によるミニレクチュア |
京都信用金庫理事長・榊田様よりテーマのご説明 |
|
 |
 |
|
| 藤本先生によるミニレクチュア |
藤本先生による計画地(会場内)ご案内 |
|
 |
 |
|
| 現地説明会の様子 |
各班のコンセプトメイキングの様子 |
|
 |
 |
|
| 各班のコンセプトメイキングの様子 |
各班で決定したコンセプトの発表 |
|

【開催記念 説明会・講演会】
ワークショップの参加募集の説明会と、開催を記念して活躍中のプランナーと建築家にレクチュアを行っていただきました。
![]()
| 東京会場 東京大学(弥生キャンパス) 農学部 弥生講堂アネックス 東京メトロ南北線「東大前駅」徒歩3分 5月8日(木)17:30-19:00(17:00開場) |
|
|
基調講演 石川勝(大阪・関西万博会場運営プロデューサー) |
||
●ひとことコメント アートアンドアーキテクトフェスタ/杉田美咲(大阪公立大学大学院 修士2年) 堀之内太視(武蔵野大学 修士1年) 松岡智大 |
||
![]()
| 京都会場 京都大学(吉田キャンパス) 百周年時計台記念館 国際交流ホールIII 文学部 第3講義室 入場無料|定員: 先着100名|要申込 |
|
|
基調講演 藤本壮介(建築家) |
||
●ひとことコメント |
||

4/4(火) アドバイザー会議 |
||
全国から応募し選出される参加学生の決定に先立ち、建築や芸術、環境やデザインを学ぶ学生(学部生・院生)らの提案・制作の指導・補助、材料提供・手配、実施におけるアドバイザー(建築技術者)の皆様に実施の交流を促すため2021年度より設けましたこの集まりは、
近い将来、我が国の建築会を担う後進に向けて、実務経験豊富な建築技術者の皆様から指導を頂戴できる、貴重な機会を共有する目的。本開催に継続的なご支援をくださる皆様や近畿を中心とする建築技術者の皆様、開催全体のスケジュールと共有し、提案作品講評会(本年:7/20日曜日)と、翌日実施制作打ち合わせ(本年:7/21月曜日)に向けて、本年の開催が始動いたしました。 |
||
 |
||
| 関係者・講評者・アドバイザーの皆様 |
||
 |
 |
|
| 2025日本国際博覧会協会副事務総長・髙科様よりご挨拶 | アドバイザー会議の様子 |
|
 |
 |
|
| 忽那先生による計画候補地のご案内 |
忽那先生による計画候補地のご案内 | |
 |
 |
|
| 忽那先生による計画候補地のご案内 | 忽那先生による計画候補地のご案内 | |
 |
 |
|
| 忽那先生による計画候補地のご案内 | 懇親会の様子 |
|

座 談 会 | ”1970から2025へ” ~未来に受け継ぐために建築ができること |
|
|
――― 全国の大学生が参加するこの建築学生ワークショップは、毎年、場所を移して開催してきました。歴史と場所の特性をはっきりと持つ開催地・聖地と、周辺の生活文化を合わせて調査することにより、観光として訪れるだけでは知ることのできない地域との関わりや、建築を保全していく造り方の技に触れ、制作を含めた実学のために地域滞在を行います。計画地の歴史コンテクストを繋いで見出し、現場で建築のつくり方や解き方を探るきっかけを経験していきます。また、この夢洲は、1977年廃棄物処分地の整備が始まり、1991年には土地造成事業が開始され、2001年夢舞大橋が完成、2009年夢咲トンネルが開通しました。これまで様々な利用計画が挙がりましたが造成開始当時に計画された事業はバブル崩壊で実現せず、オリンピック招致も失敗し、これまで負の遺産と称されましたが、紆余曲折を経て、ついに2025年大阪・関西万博の開催が決定しました。近現代における主要都市の街づくりに欠かせない島の開発と、これから最も貴重となる「聖地」に身を置き、全国から集まる建築学生らがこのあらたな地に触れ、この場に位置づける建築の解釈を生み出したいと考えています。そこでこの場所の特性を用いるため、大きく分けて「歴史」「場所性(地形)」「現代の問題」の観点から提案に求めるものやワークショップ開催の目標となる言葉や意義について模索したいと考えております。次世代を担うであろう、建築や芸術、デザインを学ぶ学生たちが夢洲に身を置き、場の空気を体験しながら学びを得ることにより、貴重な経験を通じて2025年・夏、小さな建築空間を表現します。空間性へのテーマや、実現へのコンセプトのヒントとなる話題を、この座談会を通じてお聞かせください。 本日は開催候補地として多大なご尽力をくださいます博覧会協会にて、建築や芸術、環境やデザインを全国で学ぶ参加学生に向けて導きをくださる、髙科副事務総長をはじめ、石川勝さん、藤本壮介さんにもご参加をいただき、オーガナイザーの役割を担い続けてくださいます建築家の平沼先生と共に、25年の万博会場での開催についてお聞きしたいと思います。皆さま本日はどうぞよろしくお願いいたします。 平沼:まず始めに万博の全体とテーマについて、髙科さんからお話しいただけないでしょうか。 髙科:先ほど上陸してご見学いただいた「夢洲」というUSJ近くの埋め立て地で開催する予定で、2025年4月より約半年の期間に来場者は約2,800万人を想定して開催準備を進めています。万博には「総合的な万博」と「テーマを絞った万博」の2種類がありますが、今回はそのうち大きな方の万博で、日本での開催は70年の大阪万博と05年の愛・地球博、これらに次いで我が国で3度目の開催になります。現在の準備の状況としまして、建設は23年4月の着工を目指しています。工事工区は大きく4工区に分け、それぞれの統括的なゼネコンが決定し、具体的な施工調整を始めるなか、藤本プロデューサーの大屋根(リング)の詳細イメージも発表させていただきました。全体のテーマは『いのち輝く 未来社会のデザイン』。テーマ事業のプロデューサーが8人おられ、1つずつパビリオンをつくり、それに沿う「いのち」をテーマにした世界感をそれぞれに作っていただく。そして藤本さんの考えておられる静けさの森も一つのエリアとして、大きなテーマを発信できると思います。テーマ事業というのは、70年万博では岡本太郎さんの太陽の塔、 愛・地球博では冷凍マンモスでしたが、それに次ぐ万博の顔となるプロジェクトです。プロデューサーの方々は、我々が存在している意味を問いかけて、気づきが生まれるような内容をそれぞれ独自の視点から考えていただいて、とてもワクワク感の高まる、魅力あるものになっていくのではないかと期待をしています。また、パビリオンだけではなくて、万博全体を未来社会のショーケースにしたいということで、これはショーケース事業として今後まとまったものから順次発表していくことで、世の中の関心を高めていきます。海外からは、現在約140カ国が参加表明をいただいております。10月25、26日に、IPM(インターナショナル・プランニング・ミーティング)という、各国の政府代表が初めて大阪に集まって、現場を見ていただくとともに、今後の進め方について説明し、我々とディスカッションさせていただく場がありますが、そこから海外との関係も実際にスタートすることになります。“ミャクミャク”というキャラクターも決まりましたので大いに活躍してもらって、万博でこんなことが見られるんだ、体験できるんだという期待も高め、全国で機運が盛り上がっていくような働きかけも加速していきたいと思います。また入場チケットは、23年度中に前売券の販売を開始したいと考えていますが、前売券を発売するからには、やはり魅力あるものにして、色々なPRを行って、全国での機運を高めていきたいと思っています。 平沼:石川さんは愛・地球博にも関わられたと思いますが、万博は本当に必要かという声があります。若い層には特に盛り上がってほしいなと思っているのですが、どういうメッセージを伝えたら良いでしょうか? 石川:万博と建築の話に少し触れておくと、第一回の万博は1851年にロンドンのハイド・パークを会場に、ヴィクトリア女王のご主人のアルバート公という人が率いて始められました。そこにクリスタルパレスという大きな水晶宮があったんですね。当時19世紀でまだまだ石とレンガの建築の時代だったところに、鉄とガラスの建築、それも大空間をつくるというのは画期的なことで、やっぱり万博と建築というのは切っても切れない関係性にあるのです。クリスタルパレスをつくったのは、実は建築家ではなくて造園家なんです。その方が温室の技術を使ってクリスタルパレスをつくったということを見ても、万博は常に新しい建築技術、新しいデザインの実験場だったことが窺えます。その後もたくさん万博が行われてきましたが、例えばグラン・パレとかプティ・パレ、エッフェル塔など、パリにある主要な建物は全て万博をきっかけにできています。その当時の新しい建築技術がそこで実験的につくられて世の中に出てきて、その後の街のスタンダードになっているということです。ですからこういう新しい建築の取り組みが過去の万博で見られてきた歴史があって、今回の大阪・関西万博でも藤本さんをはじめとする建築家の作品が見られることになります。愛・地球博の外国のパビリオンではモジュール形式と言って、主催者である日本側がモジュール建築を建てて、そこに外装を張り付けてやるという構造でした。今回の大阪・関西万博の敷地を渡して各国が自由に建築をつくるセルフビルド方式は’70年万博以来で、日本では50年ぶりです。ミラノやドバイなどの万博でもセルフビルド方式でしたので、各国が工夫を凝らした意匠や、構造的にもすごくチャレンジングなものが見られました。日本でそんな面白いことができる機会は建築を志す皆さんにとっては千載一遇のチャンスの場だと思いますね。万博はオリンピックと一緒で本当は参加することに意義があります。建築や周辺分野を目指している皆さんは万博にプレイヤーの一員として関わっていただけると、すごく良いと思います。振り返ると、丹下健三さんを筆頭に偉大な建築家たちは皆、万博で世の中に出てきているわけですね。若手建築家に小さな建築をつくってもらうことも一つの試みだし、建築だけではなくて、これからいろんなパビリオンでいろんなプランニングをしますから、そういうところに参加したり、自分たちの活動を「TEAM EXPO2025」として万博を通じて発信したり、会場の中での運営に携わりたいならスタッフやボランティアとして入ったり、といういろんな機会があります。せっかく自分たちが生きている時に自分たちの国で万博があるわけですから、そういうチャンスを生かしてもらえればと思います。そして万博で、「建築学生ワークショップ」が開催されるのは生きている間では一度きりになるでしょうし、大いに参加してもらえればと思います。 髙科:デザイン的にはピクトグラムも大阪万博で始まったと聞きました。そういう意味では次の時代のスタンダードになるヒントがたくさん隠れているところだと思うのです。だからこそ参加したり体験してみたりするということは、若者にとって、次の時代がどんな時代になるのかを考える上でも非常に意義のあることなのではないかと思います。かつてゼネコンさんの70年万博の記録映像を見せてもらったことがありますが、見たこともないような形状のパビリオンを、どういう技術でクリアし設計や実際の施工をするのか、建築を志す方にはめったに得られないとても良い、素晴らしい機会になるのではないかなと思いました。 平沼:生活文化を映す鏡が建築と言われます。逆に未来の生活や暮らしを予測するものが万博と捉えていけば良いのかもしれませんね。 藤本:万博では複層的に、とてもたくさんの価値観のレイヤーが入っていて、多様化した社会における特に現代の万博の特徴なのではないかと思っています。会場を設計するにあたって、「いのち」というテーマがありますが、『いのち輝く 未来社会のデザイン』というのを僕たちなりに読み替えていかないといけない。建築、会場、会場デザイン、環境デザインにおいてもこのレイヤ―が繋がるように考えていきました。いのちというのは多様なものが関係し合いながら存在します。万博は150カ国が集まるという時点で、文化も習慣も相当、多様です。それらが6ヶ月間、何らかの形で良い関係や繋がりをつくりながら共に未来を考えたり、あるいは異なる国や文化が共存していたり、新しい繋がりを見つけていくことが未来なのかもしれません。フィジカルな繋がりとは別に、時間の流れの循環もありますし、何かを受け渡してそれを他の国の人たちがどう使っていくかという意味での循環もあり得るでしょう。だからこそこの循環という価値によって生まれるサイクルは、これからの社会の大きなキーワードになってくると思います。そこでリングはやっぱり循環を想起させるということと、誰もが「つながり」をイメージすることができる象徴としてデザインしているんです。さらに真ん中に森を置くことで自然の循環や木々の生命としての循環も盛り込みたい。一方で各国のパビリオンでは、それぞれが持っている文化と未来へのビジョンを良い意味で競い合うような側面もあるので、その華やかな感じが万博のレイヤーだと置き換える。多様なものが集まることによって生まれるエネルギーを実際にドバイ博で見ましたが、それぞれの国がその国ならではの気候風土と、それをベースにした文化をちゃんと培っているというのが本当に感動的で、それを見るだけでも価値がある。そういう学びと未来が共存していると場はすごく良いことだと感じています。今までこの建築学生ワークショップは、ずっと、歴史のある聖地で開催してきました。文化や歴史的な背景に頼り、大いに手がかかりにすることで、逆に現代の建築や未来の建築をつくる時の豊かなインスピレーションになっていたと思います。万博はそういう意味では場所という意味でのコンテクストがないように見えるから、何となくかりそめのイベントみたいに見えるかもしれません。ですが、実はコンテクストは結構あって、先ほど石川さんもおっしゃっていたように万博というものの歴史があるし、それからこの場所は埋め立ての島ですが、周りを取り囲んでいる大阪・関西エリアは日本の歴史や国際交流の歴史にすごく根ざしている。いのちや多様性という概念をどう形づくるかを考えることも、大いなるコンテクストになるのではないかと思います。これからの時代の価値観を見出し、どう言葉にして、それをどう会場デザインなり建築なりに映し変えていくのかということをまさに今リアルタイムでやっています。でもそのコンテクストをそのまま引き受ける必要はなくて、それを批評的に見ても良いし、あるいはその先を考えても良い。さらに突っ込んでコンテクストなり今の世界の状況を自分たちなりに考えるプロセスは凄く価値があります。その中に持続可能な社会、それから多様なものたちが共に支えあいながら、補い合いながら共存していく社会の全体像は、2025年には常識になっていると思います。ただそれゆえに、どう実現していくのかというところはよりリアルに問われてくるのではないか。若い世代の発想力とビジョンに期待したいなと思います。 平沼:素材に関してどういうサーキュレーションを起こしていこうと考えていますか?藤本さんがおっしゃった通り、デフォルトとしてこれが一つの世界的な事例になって、それ以降建築界は素材の扱い方が変わってしまうかもしれないくらいの影響力があると思うのですが。 藤本:トータルの循環を考える良い機会なのではないかと思っています。元々寺社仏閣のような聖地だと、その敷地内でほぼ全ての循環が行われている場合が多い。それは理想的だと思うのですが、現代社会においては多少広がりのある領域の中で循環させることも意味があるのではないかと思います。周りが海に囲まれているのでその行先、持ってくる方法を含めた可能性はいろいろ広がりますし、今まで以上に能動的に考えていく。そして循環の意味を自分たちなりに「再定義」していくというのは凄く面白いと思います。 平沼:皆さんには宮島開催の様子を見ていただきましたが、この万博開催に参加される学生に、どんな希望や期待をされますか?また、実はこの万博の翌年の開催が奈良の法隆寺に決定しています。藤本さんがつくられるおそらく世界最新の木造建築がある場所から、世界最古の木造建築がある場所へ移ります。この比較からも、このワークショップの趣旨をより深く図りたいなとも考えています。参加する学生たちへ合わせてメッセージをいただけないでしょうか。 髙科:万博会場でいつどのような催事を開催するかはまだ何も決まっていませんが、それを前提に申し上げると、確かに万博は純粋な意味での聖地とは違うコンテクストが考えられると思います。参加される学生さんたちがまず、どのコンテクストから発想を深めてコンセプトを作るかという所から始まるのかなと思います。感じ方はそれぞれ違いますから、今回はコンテクスト自体、自分たちで一番強く感じるところから真っすぐにやっていく。未来社会へ向けた万博である以上、それは凄く面白いことになるのではないかなという気がしました。全体としては『いのち輝く 未来社会のデザイン』という、「いのち」が一つの大きなテーマがあって、その大きなテーマの中でそれぞれが強く感じたコンテクストで何かを作っていくという体験ができる、すごく貴重な機会になりそうです。 石川:建築学生ワークショップですが、日本を代表する聖地の方々が一堂に会するという機会は、めったにないと思いますので、この活動の素晴らしさに賛同して集まっておられるのだろうと思いますし、建築に対する社会の期待や建築業界が持っているアクティビティみたいなものがやはり凄いんだなと感じていました。聖地というのはお参りをして祈ったり、感謝したりする「営み」があるから、僕たちは聖地を聖地として感じているのだと思うのですが、歴史や未来への展望も含む営みということで考えると、万博もやはりそういう構造を持っていて、世界中から万博に出すパビリオンは、今を見つめつつ、将来に向けてこうあるべきだという提案がされていて、訪れた人はそれに向き合って自分の中の内なるものを見つめ、外に対して発信していく。ですから万博会場というのは聖地に通ずるものがあるので、建築学生ワークショップの開催場所として相応しいという文脈を持つことができると思いました。翌年、26年は法隆寺で開催するということで、世界最古の、当時の最大の木造建築の場において何らかのテーマをきっと持たれると思いますが、どうも建築業界では昔から、最初はテーマから入ったはずが、出口になると必ず意匠とか構造とか機能とか値段とかに収斂して、いつの間にかテーマがいなくなる。僕はそれがとても気になるので、折角掲げたテーマに対して手段として提案している作品がどういう意味を持つのかというところをきちんと掘り下げてもらいたいです。世界最古の木造建築と、皆がつくる作品との関連性の中で、課題やテーマに対してどのような価値があるとか、斬新だといったメッセージ性を持っているかどうかというところを問う場にして欲しいです。 平沼:ありがとうございます。その通りですね。僕も藤本さんも毎開催、伝えているつもりなのですが、だいたい無視される。なぜか聞いてくれないのです。(笑) 一同:アハハ。(笑) 石川:これこそ、日本の建築界に脈々と続いている文化でしょうね! 平沼:大阪万博が1970年、今回が2025年で、二度あることは三度あるとするならば、次の大阪万博は55年後の2080年なのかな?何となく希望と期待を持っておきたいのが大阪人の性分です(笑)。僕たちは残念ながらその頃にはこの世にいないでしょうから、このワークショップに参加する21世紀生まれの学生たちには、「当時こういうことがあったんだぞ~」という事実を継いでいってもらいたいと思うのです。ワークショップでは藤本さんの会場コンセプトをきちんと読み取り会場を見て建築に寄せて提案をする人、逆に対峙したいと挑戦してくる人が出てくると思いますが、55年後に万博があればその経験を活かしてチャレンジしてくれる人がその頃に出てきたら素晴らしいなぁと思うのです。恐らくどうしても僕たちでは直接、継げませんから、その人たちに継いでもらわないといけません。藤本さん、参加して挑戦してくる学生たちへメッセージをお願いします! 藤本:わぁ、むずかしいね(笑)。僕たちも今の信念の元にやってはいますが、それが正しいかもわからないし、50年も経つと世の中がガラッと変わるでしょう。例えば’70年万博の時には文明社会、機械、素晴らしい人工物の祭典として行われましたが、今回は自然環境やいのちがテーマです。しかし’70年に丹下さんをはじめ、建築だけではなく様々な将来を夢見たことが、今光り輝いていることは確かなんですね。それはまさに脈々と受け継がれていく中で徹底的にやり切ったことによって、それを引き継ぐ人もいれば、良い意味でポジティブに異議を唱える人もいるし、新しい価値観を打ち出す人もいる。「やり切ったこと」で、それが生み出す様々な反応がまた次の世代のクリエーションなりビジョンをつくっていくことは素晴らしいと思っています。そもそも僕たちは、100年前くらいに起こったモダニズムの動きを今も見返しながらその先を考えたりしている。「どんな小さな一歩でも未来に投げかけることはできる」のではないか。それらが多様なものと合わさって、本当の大きな未来像みたいなものとして緩やかに現れてくる。小さな一歩でも良いし、あるいは大きなストーリーを引き継ぎつつ、「その人なりの未来をつくっていく作業をずっと続けていきたい」と思ってもらいたいです。思いもよらない価値観に出会い、どんどん変化していって、それがずっと続いていくということ自体が、僕は素晴らしい出来事ではないかなと思います。 平沼:ありがとうございます!参加してくる学生の皆さんを、楽しみにお待ちしています。 (令和4年10月8日 大阪府咲洲庁舎43階 2025年日本国際博覧会協会にて) 編集後記 杉田美咲 (AAF│建築学生ワークショップ2025運営責任者) |

アーカイブ / Archive